【事例インタビュー】官民協働で拓く「切れ目ない支援」 ──赤ちゃん本舗が挑む子育て政策の最前線

官民協働で拓く「切れ目ない支援」 ──赤ちゃん本舗が挑む子育て政策の最前線
株式会社赤ちゃん本舗メディア開発部パブリックアカウントユニット 西峯佳恵 × 元経済産業省/慶應義塾大学SFC研究所上席所員 門ひろこ × キャピトルシンク代表取締役 松井亜里香
「更にスピーディに、大きなスケールで子育てをもっと安心して楽しめる社会にしていくためには、公共領域との連携が必要」そんな想いを胸に、行政と連携して子育て世代を支える新たな挑戦を始めた企業があります。
株式会社赤ちゃん本舗(以下、赤ちゃん本舗)は、妊娠期から乳幼児期までの子育て世代に深く寄り添い、行政側(中央省庁や地方自治体)も必要としている声を集めています。それらの情報やデータを政策に反映させるために行政側に届けることで、日々の生活に直結する支援の仕組みを広げています。行政だけでは拾いきれない声を民間が補い、切れ目ない支援を実現することにどのような意義があるのか。行政、民間、サービスを享受する国民にとって、まさに『三方よし』の持続可能性の高いビジネスモデルを確立しつつある事例を深掘りします。
今回は、株式会社赤ちゃん本舗 メディア開発部 パブリック アカウント ユニット 西峯佳恵 さん、元経済産業省/慶應義塾大学SFC研究所上席所員 門ひろこ さん、キャピトルシンク代表取締役 松井亜里香 それぞれの専門的な視点での対談を通じて、官民協働の現状と、その先に描く未来像をお届けします。(本文中敬称略)

※アカチャンホンポららぽーと堺店サイネージ前にて(左から:キャピトルシンク代表 松井、赤ちゃん本舗 西峯様)
1章 社会環境の変化と赤ちゃん本舗の立ち位置
少子化の波は確実に押し寄せています。共働きの増加、地域格差、制度の隙間に取り残される家庭 ──。そんな時代に、赤ちゃん本舗は「子育て世代の代弁者」として、行政が必要としている現場の声を拾い、それらを政策に反映させるために行政に届ける挑戦を続けています。
松井
赤ちゃん本舗さんが展開されている政策連携事業についてお聞かせください。厚生労働省等が運営する検討会にも、妊産婦の声を伝える有識者として参加されていましたが、昨今の子育て世代における政策課題において、特に注目しているトレンドや変化はありますか?
西峯
当社のお客様は妊娠中から乳幼児を育てている方々です。そうした皆さまの声を集めて行政側へ届けるとともに、政策を妊産婦の方々へ分かりやすく届ける取り組みを始めています。現在私たちが特に注目している課題は大きく3つあります。
1つ目は「プレコンセプションケア」です。これは妊娠前の段階からの健康管理で、子ども家庭庁も認知拡大に取り組んでいます。当社のお客様層とも親和性が高い分野で、私たちもチャレンジできることを模索しています。
2つ目は「産後ケア」です。行政が提供するサービスは受け入れ先が限られ、優先度の高い方しか利用できない一方、民間が運営する産後ケアは高額で、全員が受けられるわけではありません。手続きの簡略化や、サービス内容の情報整理と発信によって、もっと多くの方がスムーズに利用できるようにしたいと考えています。
そして3つ目は「妊産婦への切れ目ない支援」です。出産はゴールではなくスタート。産後も続く子育て支援の仕組みが重要だと感じています。
松井
これらは行政目線でも優先度が高いテーマだと思いますが、門さんはいかがでしょうか。
門
そうですね。今後、少子化がさらに進み、人数が少なくなることで必然的に子育て世代の声は小さくなります。しかしそれは政策上の優先度を下げて良いということにはなりません。子育て世代の声を拾い、発信し続け、政策に落とし込むことが不可欠です。特に子どもは選挙権も被選挙権もありません。だからこそ、政治家は声の大きい団体や世代に流されないように気を付ける必要があります。赤ちゃん本舗さんのように、子育てに特化して子育て世代と向き合い、政策にアンテナを張っていただける存在は、政治の軸をぶらさない意味でとても重要だと思います。
松井
子育て世代を限定して行政が管理するのは相当高いハードルがあるので、常に顧客情報という形で子育て世代と接点がある赤ちゃん本舗さんのような企業は行政からも感謝される存在ということですね。先日、国土交通省政務官を訪問した際にも、「子育ては国土交通省のまちづくり政策にも直結する」と歓迎いただきました。厚労省に限らず、子育てに関わらない省庁はほとんどなく、むしろ多くの分野で「ありがたい」との声をいただいています。社会全体で子育てを支える必要性を、改めて実感する場面でした。西峯さんは、企業としての社会的役割をどう捉えていますか?
西峯
当社は創業から90年以上の歴史があります。もともとは卸業からスタートし、その後小売に転換しました。この十数年は、単なる物販ではなく、カスタマーエクスペリエンスの向上を目指してきました。例えば、出産予定日やお子様のお誕生日、居住地域などのデータを活用して、妊娠・出産・子育てのフェーズや、地域に合わせておすすめの商品情報やイベント情報、妊娠・出産・育児に関わる情報をプッシュ型で届けるなどです。これらの情報やツールは、行政にとってとても魅力的なアセットだということに気づきました。我々は子育て世代を代表する企業の責任として、子どもを産み育てやすい社会づくりに貢献することが必要だと考えています。

松井
歴史ある大企業だからこそ、短期利益だけでなく社会全体の視点を持てるということですね。独自の強みはどこにありますか?
西峯
コアターゲットが明確である点です。妊娠から生後2〜3歳の子どもを持つ方という属性に絞っているため、会員基盤には詳細な情報があります。妊娠中と産後では必要な情報が異なりますし、生後半年、1歳、2歳と成長に応じて変わります。その時期に必要な情報だけを適切に届けられるのは当社の強みです。
門
行政は個人情報保護やリソース制約等の観点から、ここまで細かい生活データを収集・活用できません。普通に暮らしている妊娠中や子育て中の方の小さな困りごとは、行政には届きにくいのです。そこを可視化できる赤ちゃん本舗さんの存在は、行政との相互補完関係を築く上で大きな意味があります。
2章 なぜ今、政策連携なのか?
企業が政策連携に踏み出すとき、自社の利益追求にとどまらず、社会課題の解決を企業の使命に据える動きは、どのようにして形づくられるのか。赤ちゃん本舗が政策連携部門を立ち上げた背景と、行政から見たその意義をひも解きます。
西峯
一昨年頃から取締役執行役員の土師(当時マーケティング本部長)を中心に、社内のメンバーと共に、「子育て総合支援企業としてやるべきこと」を改めて考える機会がありました。当社は10年以上その旗を掲げてきましたが、立ち止まって再検討したのです。具体的にやるべきことを洗い出す中で、「お客様の声を代弁して社会に届ける活動が必要」という結論に至りました。当社は妊産婦の方々と直接コミュニケーションを取れる立場にあります。そこで得られた声を集め、世の中や行政側に伝えていくことが、より良い子育て環境づくりにつながると考え政策連携部門を立ち上げました。また、行政と連携することで、会社のミッションやゴールにより早く近づけるという感覚もありました。
松井
門さん、行政の立場から見ると、こうした企業の動きはどのように映りますか。
門
非常にありがたいですね。私は経済産業省にいましたが、企業が行政に手を差し伸べ、うまく活用しようとしてくれること自体が貴重です。かつては陳情型、つまり「地元に道路を引いてほしい」「産業を守ってほしい」といった自己・自社利益中心の要望が多かったのです。しかし赤ちゃん本舗さんの場合、日本の少子化対策という公益的な課題解決と、自社の将来の顧客創出という企業のインセンティブが見事に重なっています。これは行政のニーズと全く齟齬がない好例です。

松井
行政・顧客・企業の全てに利益がある、まさに三方良しですね。
門
そうですね。少子化によって、子育て世代のニーズや実態の発信能力が相対的に低下する中、行政にとっては心強いパートナーです。さらに、赤ちゃん本舗さんは公益という目線を持っており、それが自治体や省庁からも信頼される要因になっています。
松井
ただ、今まで公共事業部がなかった民間企業にとって、政策連携って簡単ではないですよね。西峯さん、実際にやってみて難しさを感じる部分はありましたか?
西峯
そもそもステークホルダーの文化や背景が異なります。中央省庁、自治体、生活者、民間企業…それぞれ見えているものが違い、共通言語や共通認識がまだ十分にありません。だからこそ、地道にコミュニケーションを続けることが大事だと痛感しています。
松井
門さん、民間側がここまで歩み寄ってくれている中で、行政側はどうすべきだと思われますか。
門
行政も、昔のように「自分たちで情報を集めて終わり」という発想から脱却すべきです。むしろ民間企業の知見を積極的に借りるべきですし、それをお願いできる姿勢が必要です。ただし注意点もあります。特定企業だけと付き合うのではなく、幅広くオープンな組織文化を作ること。そうしないと、結局は一部の業界団体やOBネットワークだけで話が完結してしまう危険があります。
松井
確かに、行政側にも民間との協働体制づくりが求められますね。
門
はい。組織としてオープンさを標準化し、柔軟な政策立案ができるようにする。それが国レベルでも地方レベルでも必要だと思います。
3章 キャピトルシンクとの協働と伴走支援の意義
行政と民間。異なる文化や時間軸を持つ相手と成果を出すためには、どのような知見やつなぎ役が必要なのでしょうか。赤ちゃん本舗がキャピトルシンクと協働することで得られた変化と、行政から見た「伴走支援」の価値について伺いました。
松井
キャピトルシンクのコンサルティングを受けてみて、赤ちゃん本舗さんにどのような変化がありましたか?
西峯
一番大きかったのは、中央省庁や自治体の構造、そして年間の政策スケジュールを理解できるようになったことです。例えば予算編成の時期や、どのタイミングで政策が動くのか。そうした行政特有の時間軸を把握できたことで、私たちの活動計画も立てやすくなりました。また、実際に成果が出始めると、社内の理解が一気に進みました。経営層も「こういう形で行政と関わっていくのか」とイメージしやすくなったと思います。

※子育て支援に積極的な自治体にて、赤ちゃん本舗の政策連携サービスの説明を行う西峯さん (隣はキャピトルシンク代表松井)
松井
社内の理解は重要ですよね。門さん、今回赤ちゃん本舗さんとの政策伴走支援に取り組んでみていかがでしたか?
門
赤ちゃん本舗さんは「日本全体にとっても良いこと」をしているというストーリーが明確でした。そのため行政との連携を進める際にも非常にやりやすかったです。実際に私自身、関連政策に詳しく子育てに理解ある衆議院議員、参議院議員を訪ねた際にご一緒しましたが、若い世代の政治家ほど子育て支援への理解や関心が高く、反応も非常に前向きでした。政策実現のポイントの一つは、「誰と繋ぐか」「どのタイミングでどのボタンを押すか」を見極めることです。赤ちゃん本舗さんの場合、関心を持ってくれる若手政治家や、省庁内で子育て政策に熱心な担当者にしっかりアプローチできたのが成功の要因ですね。
 ※衆・参議院議員を訪ね、子育て支援策について意見交換を行った際の様子 ※衆・参議院議員を訪ね、子育て支援策について意見交換を行った際の様子 |

|
松井
確かに、政策連携ではストーリーと人脈の両方が大事になります。私自身もご紹介を通じて「イケてる」行政人材や、民間と協働する意欲のある方々に繋ぐことを意識しました。実は政府組織の人事は必ずしも個人の興味関心や経歴をダイレクトに反映しているわけではないので、適切な部署だと思って正面から問い合わせてみたが担当者が塩対応だった、というのはあるあるなのです。「イケてる」を言語化するのは難しいのですが、民間視点がある・新しいテクノロジーやツールにチャレンジするキャパシティがある・色んな部署とのパイプを持っていて話が通せる、などといった特徴をもつ行政人材を「イケてる人」と呼んでいます。結果的にご紹介した行政人材から具体的な動きにつながった案件も多かったと思います。

西峯
はい、まさにそうです。自分たちだけではなかなか接点を持てなかった方々と出会えたことは大きいです。行政との関係づくりは、一度の面談で終わることはなく、継続的なコミュニケーションが必要です。キャピトルシンクさんの伴走があったことで、その継続が途切れずに済みました。
門
そして、単なる橋渡しではなく、行政が関心を持つ切り口に沿って提案内容をブラッシュアップしてくれる。これは外部伴走者ならではの価値だと思います。民間企業が単独で政策連携に挑むと、どうしても自社目線の提案になりがちですが、そこを公益性の高い形に整えてくれた印象です。
松井
私たちとしても、赤ちゃん本舗さんの現場知見を活かしながら、行政にとっても受け入れやすいストーリーにして届けることを意識していました。政策領域では、この「伴走」の意義がとても大きいと感じます。
4章 実例から見る、官民連携のリアル
行政と民間の連携は、理念だけではなく現場での実践によって形になります。国や自治体との協働事例からは、双方の強みや課題、そして連携によって生まれる具体的な成果が見えてきます。赤ちゃん本舗が取り組んできた官民協働の実例と、その現場で感じた手応えについて伺いました。
松井
赤ちゃん本舗さんとして、これまでにどのような政策連携をされたのでしょうか?
西峯
大きく分けて国と自治体、それぞれで事例があります。
まず国の事例として、妊産婦等の支援策等に関する検討会で発表の機会をいただきました。内容は、当社が実施した妊産婦向けアンケートです。わずか3日間で7,500件の回答を集め、現場の声をエビデンスとして提示できたことが評価されました。また、国土交通省からの依頼は、授乳室やトイレ利用のニーズ調査、公共交通機関利用状況調査の周知でした。
 |

※アカチャンホンポアプリから行政が発信している「出産なび」にアクセスが可能。 |
松井
国レベルの政策検討に直接関わりつつ、事業性をしっかり確保できるようになってこられたんですよね。自治体との連携はどうですか?
西峯
自治体では、堺市や葛飾区と協働しました。堺市では行政のポータルサイトを周知するための情報発信の支援を行い、葛飾区ではベビーカー・抱っこ紐等の購入費助成に関する情報発信を共同で強化しました。当社が小売としての営業活動の中で培ったマーケティング知見を活かし、告知物の見せ方や情報の届け方を工夫しました。

※実際に大阪府内の店頭サイネージで流れている、堺市との協業案件の映像(写真はアカチャンホンポ ららぽーと堺店)
松井
現場の反応はいかがでしたか?
西峯
店舗スタッフからは、「お客様に行政サービスを案内できてよかった」という声がありましたし、利用者の方からも「こんな制度があるなんて知らなかった」という反応をいただきました。実感として、行政情報が生活者に届くスピードや到達率が上がったと感じます。
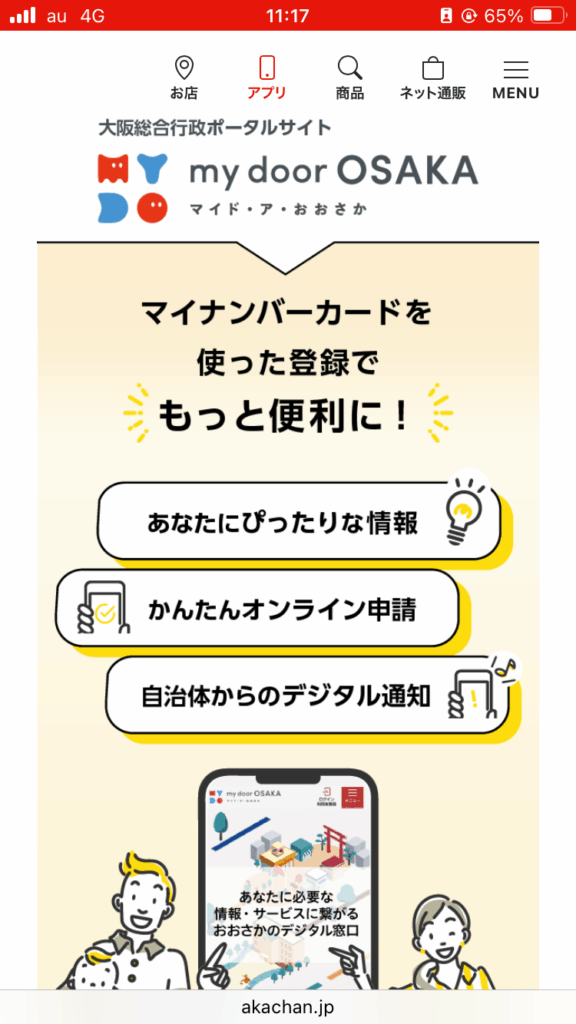
松井
門さん、行政側から見て、こうした民間との連携事例はどんな意味を持つのでしょうか。
門
まず、行政はパートナー企業を選ぶときに「生活者へのリーチ力」と「信頼性」を重視します。赤ちゃん本舗さんのように特定層へ深くリーチできる企業は貴重です。また、現場での対応力も評価されます。特に自治体側は、連携先が単に情報を渡すだけでなく、どうすれば生活者に伝わるかまで考えてくれると助かります。
松井
実際に自治体と組むと、行政と民間で考え方の違いもありますよね。
門
そうですね。行政は公平性を重視するため、民間のようにターゲットを絞った発信がしづらいことがあります。そこを赤ちゃん本舗さんのような企業がカバーしてくれると、行政側も柔軟に動けるようになります。
松井
確かに、民間ならではのスピード感や柔軟さが活きる場面ですよね。キャピトルシンクとしてもエンドユーザーである国民にプッシュ型で届けられるリーチ力とターゲティング力、例えば赤ちゃん本舗さんであれば子育て世代にピンポイントで届けられる点に注目しています。政府のホームページやSNS、アプリも、民間の集約型のウェブ上での政策サイトでもこの二点に関しては今まで実現できていなかったので、リテールメディア※1との連携によりずっとアプローチしたかったこの課題が解決できることを期待しています。
※1リテールメディアとは、小売業者が自社の顧客データや店舗・ECサイトなどの販売チャネルを広告媒体として活用し、メーカーなどの広告主に提供するビジネスモデルのことです。顧客の購買行動に合わせた広告配信が可能となり、精度の高いマーケティングや新たな収益源の創出に繋がるとして注目されています。
5章 リテールメディアの未来と、他社へのメッセージ
小売業は、単に商品を届けるだけの存在から、情報やサービスを届ける「メディア」としての役割を担いつつあります。その発信力を行政との連携に生かすことで、社会課題の解決にも貢献できる可能性があると、西峯さんは語ります。
松井
今後、赤ちゃん本舗さんとしてどのような形でこの取り組みを広げていきたいと考えていますか?
西峯
将来的には、赤ちゃん本舗を妊娠・出産・子育て期の方々にとっての大きなプラットフォームにしたいと考えています。物販だけでなく、行政や他企業と連携し情報やサービスをワンストップで提供できる場にする構想です。例えば、自社アプリに「入り口」の機能を持たせて、そこから自治体のサービスや必要な情報につながるようにしたいと思っています。
松井
単に商品を売るだけでなく、情報やサービスのハブになるわけですね。店頭やデジタルで行政情報を発信する際には、どんな工夫をしていますか?

西峯
まず、利用者の立場に立って情報を選び、分かりやすく整理することです。行政の広報物は正確ですが、生活者からすると情報量が多すぎたり、言葉が難しかったりします。そこで私たちが間に入り、「この時期の方にはこの情報を、この時期の方にはこの表現を使って」と調整をしています。
松井
私も中央省庁の戦略広報アドバイザーとして仕事をしていた時、こういった行政の広報の課題をよく相談されていました。行政は公平性や正確性を訴求力よりも重視するため、どうしてもキャッチーさが失われます。実際にエンドユーザーである国民に使ってもらわないと意味がない政策は民間広報の訴求力と届ける力が必要なことが多くあると感じます。門さん、行政の立場から見ると、企業がこうした「政策発信者」になる可能性はどう感じますか?
門
今は行政だけが政策を担う時代ではなくなっています。特に生活に密着した分野では、企業が政策発信者になる可能性は大きいです。赤ちゃん本舗さんのように、特定のライフステージに強い企業は、その分野での情報発信拠点になれる。行政としても、信頼できる民間チャネルを持つことはメリットがあります。
松井
では、政策側から見て、連携が進めやすい企業にはどんな特徴がありますか?
門
まずは公益性が高いこと。次に、ターゲット層との接点を持ち、その層の信頼を得ていること。そして、行政の意図を理解し、双方向のやり取りができる柔軟さです。さらに言えば、企業内に西峯さんのように行政との接点を理解し、共通言語で話せる担当者がいることも大きいですね。そうでないと、せっかくの取り組みも意思疎通の段階で止まってしまうことがあります。企業としてはこういった方の育成が重要かと思います。
松井
キャピトルシンクとしても、この政策渉外担当の方の育成をサポートさせていただいています。共通言語という点では、役人が使う言葉通称『霞ヶ関用語』なんかも都度コンサルティングサポートの際に解説していたりします。赤ちゃん本舗さんも最近では「ポンチ絵(役所特有の説明資料)形式にできますか?」とお伝えしても、スムーズにご理解いただけます(笑)民間企業と全然違うカルチャーの外部との連携部門の立ち上げで西峯さんは本当に大変だったと思いますが、引き続き質問などあったらすぐご相談いただき、こちらもサポート体制を充実させていきたいと思います。
西峯
ありがとうございます。これから政策連携部門も人を増やして拡大したり、社内の人材育成にも注力しつつ、今後は他社との連携も広げ、より多くの子育て世代に必要な情報とサービスが届くようにしたいです。行政や民間の枠を超え、「この分野なら赤ちゃん本舗に行けば必要な情報が揃う」と言ってもらえるような存在を目指します。

6章 これからの子育て政策と、赤ちゃん本舗が描くビジョン
「切れ目のない支援」を実現すること ——妊娠期から出産、そして育児の各段階で必要なサポートが途切れない社会をつくるための、未来に向けた具体的な連携アイデアについて伺いました。
松井
最後に、これからの子育て政策や今後のビジョンについて伺います。西峯さん、今後、政府や自治体とどのような政策連携をしていきたいと考えていますか?
西峯
これからは、より一層「切れ目のない支援」を実現していきたいと考えています。妊娠期から出産、そして子育ての各段階で必要な支援が途切れないよう、行政と連携しながら制度やサービスをつないでいきたいです。また、全国の自治体や省庁とネットワークを築き、地域差による情報・サービス格差をできる限り減らしていくことも目標です。
松井
具体的にやってみたい政策連携のアイデアはありますか?
西峯
例えば、妊産婦向けアンケートや店舗での声の収集を継続し、その結果を行政と共有して施策改善に役立てることです。現場からのリアルな声をタイムリーに届ける仕組みを作ることで、政策のスピード感も上げられると考えています。さらに、赤ちゃん本舗の会員基盤や店舗網を活用して、行政の施策を広く・深く生活者に届けるハブになりたいですね。
松井
門さん、政策側の立場から、今後赤ちゃん本舗さんに期待することは何でしょうか。
門
子育て世代の声を集め、それを政策に反映する「翻訳者」としての役割です。特に今後、子育て層の人口は減りますから、その声を行政が拾いきれないリスクが高まります。赤ちゃん本舗さんのように直接生活者と接点を持ち、かつ公益性を意識できる企業は、行政にとって頼れる存在です。また、政策連携を通じて他の民間企業にも刺激を与え、「自分たちもやってみよう」という流れを作ってほしいです。
西峯
はい。私たちは、行政・民間・市民をつなぐ架け橋のような存在を目指しています。赤ちゃん本舗という存在が、子育て世代の安心感や信頼感につながり、社会全体の子育て環境を底上げできるよう、今後も取り組みを続けていきます。
松井
確かに、官民協働は一社だけで完結するものではなく、横の広がりがあってこそ大きな力になりますね。キャピトルシンクとしては、このような成功事例や西峯さんのようなロールモデルを他の業界や政策でも横展開したいと考えています。

※アカチャンホンポ ららぽーと堺店
これまで届きにくかった子育て世代の声を集め、それを社会に届ける。
赤ちゃん本舗は、日々の現場で拾った小さな声を政策につなぎ、未来の子育て環境を形作ろうとしています。
行政の枠も企業の立場も越えて、同じ方向を見つめながら課題解決に向けて連携・協働する ——その先にあるのは、まだ見ぬ「政策が国民に届く」社会の姿です。
一つひとつの声が、しっかりと政策形成の場に届き、明日の支えへと変わるように。
行政と民間が紡ぎ、政策広報のあり方を変革する挑戦は、これからも続きます。
PROFILE

西峯佳恵(株式会社赤ちゃん本舗メディア開発部 パブリックアカウントユニット)
【経歴】神戸大学発達科学部卒業。大学では乳幼児発達や子育て支援を専攻。2010年、株式会社赤ちゃん本舗に入社。店舗勤務を経て、分析部門、広報、デジタル部門(ホームページ・アプリ・SNSなど)を担当。のべ約3年間の産休・育休を取得し、2児の母。現在は政策連携担当として、省庁や各自治体と連携し、新しいビジネスのかたちを模索している。

門ひろこ(元経済産業省/慶應義塾大学SFC研究所上席所員)
【経歴】東大法学部(女子ラクロス部主将)、米国コロンビア大学ロースクール卒業。米国NY州弁護士の資格保有。経済産業省(通商&エネルギー中心)に入省し、資源エネルギー庁、通商機構部総括係長、課長補佐を担当。元通商戦略室長(経済安保)初代ビジネス人権室長。官邸に出向。現在、慶應義塾大学SFC研究所上席所員。

松井亜里香(キャピトルシンク代表取締役)
【経歴】1994年生。アイルランド国立ダブリン大学トリニティカレッジ社会学部卒業。国会議員秘書としてキャリアをスタート後、外資系GR(政府広報)および政府広報コンサルティング会社に勤務。2023年、総務省戦略広報アドバイザーに就任し、広報改革を推進。2024年春、株式会社キャピトルシンクを設立し、代表取締役に就任(現任)。同年、一般社団法人政策広報DX協会の代表理事に就任(現任)。

 広告主の種類から探す
広告主の種類から探す
 カテゴリから探す
カテゴリから探す ターゲットから探す
ターゲットから探す
 場所から探す
場所から探す